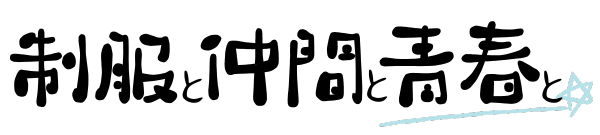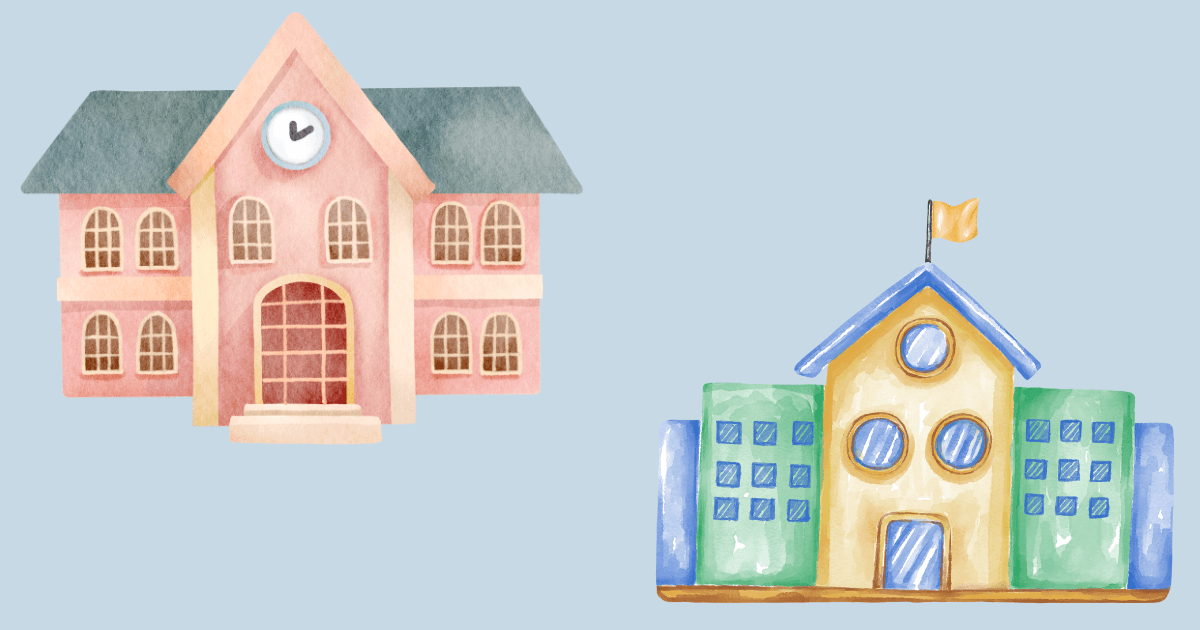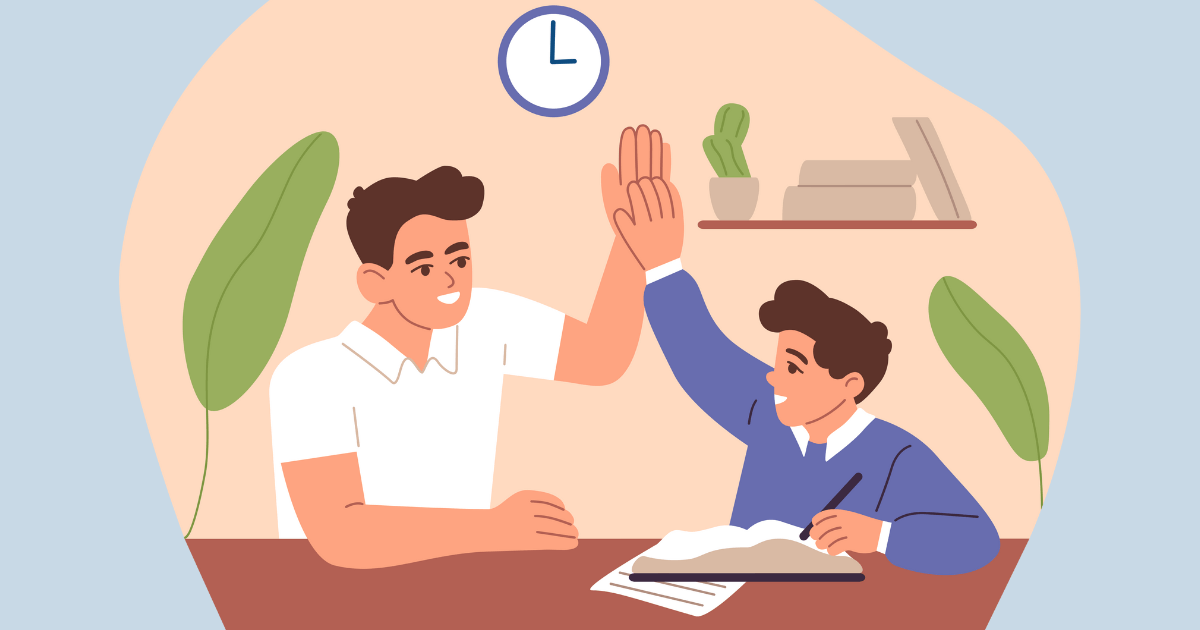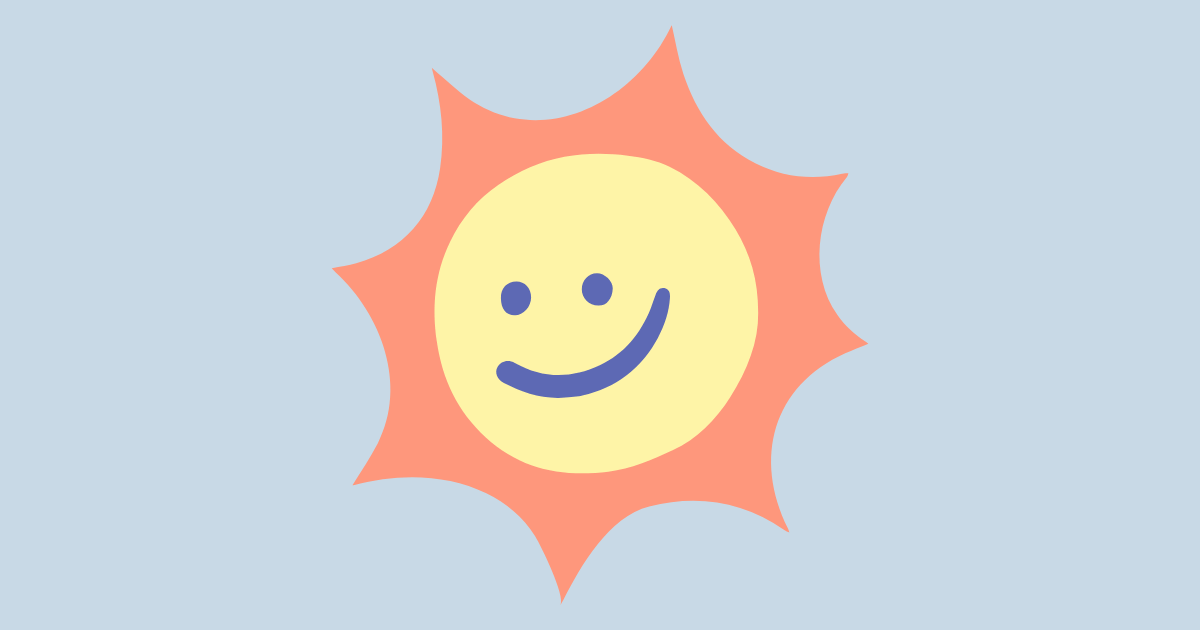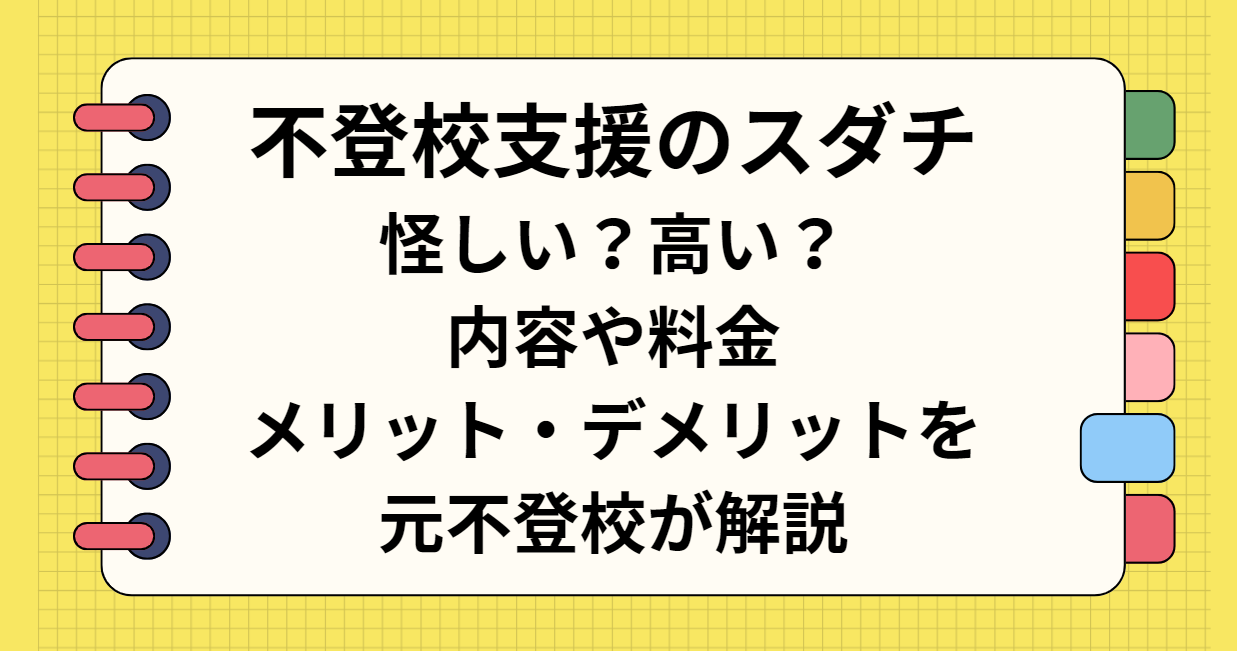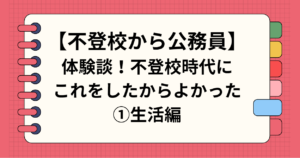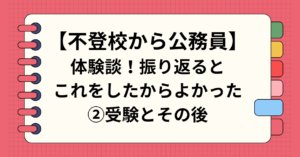「3週間で不登校を解決」のスダチって、どうなの?
無理やり登校させても意味ないし・・・。



元不登校目線でスダチの内容やメリット・デメリットをまとめました。


- 小1~不登校。中学はほぼ行けず成績オール1
- 全日制高校→公立大学→就職→転職で公務員→現在は2児の母
- 不登校受験成功の経験から不登校向けの勉強法や受験対策を発信
不登校支援サービス【スダチ】とは
スダチは民間の不登校支援サービスです。
スダチの広告↓


正直、私はこの広告を始めて見たとき
けしからん!!
無理やり再登校させてどうすんねん!かわいそう!!やめて!!
…と感じました。



子どもをなんとか丸め込んで、無理やり再登校させてる感があったからです。
広告戦略ミスってるよ絶対・・・。
しかし、深く調べ、代表の方の書籍『不登校の9割は親が解決できる』を読むと、考えが変わりました。
というより、「これ、うちの家の話!?」がいくつもあって、逆に私が不登校から復活した理由を解説されたような気分になりました。



母は、私に対してスダチ的なアプローチを取っていたようです。
一方で、スダチの支援は、ご家庭の教育方針や子さまの個性に合わない可能性もあります。
また、再登校を目指すことが本当にお子さまのためになるのか?という根本的な問題もあります。
そのあたりのデメリットについても書きましたので、スダチが気になっている方はぜひ、この記事を最後まで読んでみてくださいね。
スダチは怪しい?
不登校が身近な人ほど、スダチの広告を見て「怪しい!!」と思われる方は多いのではないでしょうか。
私の疑いは、主に次の3つでした。
- 3週間で無理やり解決してるんじゃ?(不登校ビジネスでしょ?)
- 90%以上が再登校って、1回でも登校したらカウントしてる?(継続できてるの?)
- 子どもにどんなアプローチしてるの?(無理させてない?)



しかし、『不登校の9割は親が解決できる』の冒頭だけで、これらの疑いが晴れました。
①3週間で無理やり解決してるわけじゃなかった
スダチは、「無理やり学校に連れて行っても解決しない」と主張しています。



大納得!!!
「3週間で再登校」の本当の意味は、
スダチのサポートによって本人が「頑張ってみよう」「なんとかなるかも」と思えるまでに平均約3週間かかる
ということでした。
②「90%以上が再登校」!?再登校の定義は??
90%超が再登校だなんて、一体どんな数字マジックを使ってるんだろう・・・と感じた私ですが、数字マジックではありませんでした。
- 「再登校」=朝から放課後まで2日連続で元のクラスに登校すること
- 五月雨登校※、保健室登校、午後からの登校は含まない
- 2日連続登校してもその後欠席が続いた場合はカウントしない
このような基準で再登校をカウントし、再登校率が91.4%とのこと。



きちんと「再登校」を定義していて、好印象です。
※五月雨登校・・・週に1~3日程度登校する状態
③スダチの支援対象は子どもではなく「親」
スダチは「子どもに会わずに再登校に導く」という新しい不登校支援の形を取っています。



ど、どうやって!?
具体的な支援の内容についてはこれからご紹介していきます。
スダチの提唱するメソッドの内容とは?
スダチの支援内容は、代表の小川 涼太郎氏の書籍(『不登校の9割は親が解決できる』)にてその具体的な中身が公開されています。
子どもが自ら再登校する家庭の5つの条件とは、
- 子どもの自己肯定感を高める
- 正しい生活習慣に戻す
- 正しい親子関係を築く
- お子さんが考える時間を与える
- マインドセットを変える
です。
(公式サイトで公開されているため掲載しました。)
スダチの具体的なサービス内容



わかるような、わからんような・・・?
ざっくりと勝手に言い換えさせてもらうと
- 親→子へのアプローチを変える
- 家庭内でルールを作る(生活習慣・デジタル機器)
- 困難を乗り越えられるマインドセットを育てる
ということになります。
スダチは、これらを達成するための具体的かつ個別的なアドバイス(声かけの仕方、タイミング、親が見せるべき態度、考え方など)を保護者向けに行います。
不登校の原因の追及や、お子さまへの直接的アプローチはしません。
親が変わることで家庭の環境(親子関係)を良くし、子どもの心のパワーを溜め、学校に行く気持ちを取り戻させるという流れを一緒に作っていくイメージです。
そもそも再登校は必要か?という議論
スダチを利用するとなると、再登校をゴールに進んでいくことになります。
再登校を目指すことが本当にお子さまのためになるのか…?難しいですよね。
私個人としては、「親子で模索していけば答えがでる」のだと思います。
その模索のひとつとして、スダチ的なアプローチを試してみる価値はあると考えます。
ちなみにスダチのこの議論への考えは
「学校だけがすべてじゃない(中略)が、学校に行かずに、学校と同等の教育や機会を得ることはかなり難しいのが現実」
です。



この主張には大賛成です。
残念なことに今の日本では、学校という枠が最強で、そこから外れてしまうと失うものが大きいのです。
また、学校に行かずに学校レベルの教育と運動等を私費で補う場合、少なくとも月25万円程度は必要であるとしています。
それほどの成長機会(しかも貴重な子ども時代!)を逃していると知ると、簡単に「学校が嫌なら休めば良い」とは言えないですね。
スダチの不登校支援のここに共感!



ここからは、元不登校の私から見て共感できるポイントをご紹介します!
【共感①】デジタル機器から離れることの重要性
スダチの主張の中でも特に共感できて、実体験としても効果を感じているポイントが「デジタル機器の制限」です。
スダチは、不登校を長引かせている大きな要因として、スマホ・ゲーム・YouTubeなどの依存性の高いデジタル機器を挙げています。
不登校とデジタル機器の相性は最悪で、学校を休んでいる間にデジタル依存が進んで再登校が遠のく事例が多いとのこと。
そこでスダチは、不登校の間はデジタル機器を制限するルールを作ることを提唱しています。
※書籍では、具体的なルールの作り方やお子さまへの伝え方、反発されたときの対応などが解説されています。



実は私も、学校を休んでいる間のルールとして「パソコンとテレビゲーム禁止」がありました。
こっそりやっちゃうときもありましたけどね。
私の時代はスマホやYouTubeはありませんでしたが、大人になった今でも気を抜くとハマってしまうSNS等の沼・・・、恐ろしいです。
私が最も共感したのは、日中にデジタル機器に依存することにより、不登校である自分自身のことや将来について考える時間がなくなる、という点です。
私は、パソコンもゲームも禁止されていたため、日中ほんとにやることがありませんでした。
やることがないと、いろいろと考えるもので、
「あーヒマだ。みんな今ごろ授業受けてるのか・・・」
「あ、低学年の子の下校の声が聞こえてきた・・・もう○時か・・・」
「昨日、お姉ちゃんは国語の教科書の音読してたな・・・」
「私、将来、どうなるんだろう・・・このままでいいんだろうか・・・」
不登校中、そんなことをぼんやり考えていたことを思い出しました。
以下、『不登校の9割は親が解決できる』より引用(P93-94)
「何もやることがない」ということが大事なのです。
やることがなければ、子どもはいろいろと考えます。
(中略)
ヒマな時間をつぶして目を背けさせるのではなく、向き合っても大丈夫な環境をつくりましょう。
ただぼーっとしているようでも、その時間が大事なのです。
ぼーっと考えていたあの時間、無駄じゃなかったんだ・・・!
その時間があったから、不登校を乗り越えて今の人生があったのかも。
そんな風に感じました。



パソコン、ゲーム禁止ルール、あってよかった・・・。
【共感②】子どもに会わずに再登校に導く
スダチの不登校支援の大きな特徴の一つは、支援対象がお子さまではなく「親」だということです。
私は長年不登校で、学校の先生や保健室の先生、スクールカウンセラー、精神科医…、あらゆる大人たちに
「なぜ学校に行きたくないの?」
「気持ちを教えて」
などと言われ続けて、勝手ながらその背後に「学校に行きなさい」という圧を感じてきました。
とにかく、親以外に「学校に行きなさい」と言われても、敵認定するだけだったのです。



他人にあれやこれやアプローチされても、しんどくなるだけ…。
個人差はあると思いますが、当事者のお子さまに直接関わらないスダチの支援の形は、評価できます。
【共感③】見守るだけでは解決しない
私のころとは違い、現代の不登校に対するアプローチの主流は「見守り」です。
実際、書籍によると、スダチへの相談者の90%以上は、「見守りましょう」「様子を見ましょう」というアドバイスを受けているとのこと。
それに対し、「見守るだけでは解決しない」というのがスダチの考え方であり、私も強く共感しました。



それは、私の母が、見守るだけではなく、あれやこれや手を替え品を替え(?)やってきてくれたからです。
もし母が見守っていただけなら、何も言われないのを良いことにやるべきこともやらずに生きて、今ごろ半生を後悔して日々を過ごしていたと思います。
スダチのメリット・デメリットは?



スダチを利用するメリットやデメリットが知りたい



口コミなどの調査でわかったメリット・デメリットを解説します!
スダチのメリット
- 「見守りましょう」から抜け出せる
- 親子関係が良くなる
- 途中で辞められる
メリット①「見守りましょう」から抜け出せる
再登校率90%とはいえ、スダチを利用すれば必ずお子さまが元気に再登校できるようになるとは限りません。
しかし、確実に言えるのは、「見守るだけ」という状況からは抜け出せるということ。
特に、高校進学を考えているなら、再登校に向けてなにか行動した方が良いです。
不登校だと内申点が不利



再登校できずに高校受験で苦労した私が言うので、間違いない。
無理やり行かせるのはNGですが、見守るだけではなにも変わりません。
メリット②親子関係が良くなる
スダチの利用者アンケートによると、8割以上の方がスダチ利用後に親子関係が良くなったと回答しています。
良い親子関係は、なにをするにもお子さまの大きな力の源になります。
私の場合、不登校にも関わらず進学、就職・・・と頑張って進んで来られたのは、良い親子関係(家族関係)があったからだと思っています。
一生続く親子関係が良くなるというのは、ご家庭にとって大きなメリットですね。
メリット③途中で辞められる
メリットと言えるかわかりませんが、スダチは有料サポートを開始したとしても、途中でやめることができます。
お子さまが再登校するまで続けなければならない…、と思うとなかなかハードルが高いですよね。
合わないと感じられた場合はもちろん、「これ以上は出費が厳しい」となっても辞められるので安心ですね。
スダチのデメリット
- 合わない子(家庭)もいる
- 料金が高い
デメリット①合わない子(家庭)もいる
スダチメソッドの結果が出るかどうかは、やってみなければわかりません。
個人的にはスダチメソッドは一定の効果はあると感じますが、不登校の形はさまざまなので、万人に効果があるとは思いません。



また、繰り返しになりますが、再登校を目指すことが常に正しいとは思いません。
- 明らかに学校になにか嫌なこと(人)がある
- 学校に行くのが死ぬほど嫌だと感じている
このような場合は、スダチメソッドの効果は限定的かもしれないと個人的に感じます。
私がスダチメソッドが合いそうと感じるお子さまは次のようなパターンです。
- HSC(繊細な子)気味で学校がしんどい
- 頑張り屋なのに学校を休みだしてしまった
- 勉強が嫌いではないのに学校が嫌になってしまった
- 小さなことがきっかけで学校を休みだしてそのままズルズル休んでいる
- 学校を休んで昼夜問わずゲームやスマホばかりやっている
ご自身のお子さまやご家庭にスダチメソッドが適しているかは、初回相談で聞いてみることもできますよ。
同じようなタイプのお子さまの事例なども教えてもらいましょう。
また、利用者の口コミを見ていると、スダチメソッドが合う場合は目に見えてお子さまの様子が変わってくるようなので、お子さまをしっかり見てあげることが一番大切です。
デメリット②料金が高い
あまり大々的に書かれていないスダチの利用料・・・気になりますよね。
調べたところ、スダチの再登校支援はこのような料金になっています。(2025年2月現在)
| ①初回相談(30分) | 無料 (オンライン・顔出し不要) |
|---|---|
| ②再登校面談 | 49,500円 (再登校までの計画書や対応マニュアル) |
| ③伴走再登校サポート (週3・毎日) | 55,000円~ (ヒアリング&アドバイス) |
初回相談でアドバイスをもらったり不明点を明らかにしたうえで、次の有料面談に進むかどうかを決めます。
有料サポートに移行し、毎日のサポートを1ヶ月続けるとすると、少なくとも約10万円はかかる計算になりますね。
1カ月で習いごとのお月謝1年分・・・といったところですね。
一般的な行政の不登校支援や相談窓口は無料なので、高いと感じるのも当然です。
どう感じるかは人それぞれですが、ネットの情報を見ていると、
- 実際に再登校した方は「やってよかった」
- 利用していない方、初回相談で終わった方は「高い」
と感じているようです。(そりゃそうか)
【結論】書籍を読む&無料相談してから判断しよう



不登校支援のスダチの考え方や支援内容、メリット・デメリットなどを、元不登校の個人的な意見を交えながら解説しました。
ここまで読んでくださった方は、それだけお子さまの不登校への悩みが大きいのだと思います。
そのような方に向けての私の提案は、
- 『不登校の9割は親が解決できる』を読んでみる
- 考え方に共感したら初回相談(無料)してみる(公式サイト)
- 有料支援に進むかどうか判断する
このような流れで決めることです。なぜなら、先に書籍に目を通した方が、無料相談で深い話ができるからです。
※現在、初回相談は混み合っているようです。先に仮押さえしておけば無駄がありません。(フォームは公式サイト)
不登校は長引くほど再登校が遠のきます。(私のように…!)
そして、再登校が遠のくほど、高校受験のハードルが高くなるのは事実です。無料相談だけでも、なにかヒントになるような気づきが得られるかもしれないので、ぜひ一歩踏み出してみてくださいね。
この記事が少しでも、お子さまの不登校で悩む保護者の方の役に立てれば幸いです。